こんにちは。
元幼稚園教諭・元保育士で3児の母のちょこママと申します!

ちーちゃん(小3)よっちゃん(小1)こーくん(2歳児)の3人の子育て真っ最中です!
子どもの集中力って気になりますよね‥
私は長女ちーちゃんが5歳の頃は
「小学校入学に向けて子どもの集中力を高めたい!」
と思っていましたし、ちーちゃんが実際に小学生になると
「(勉強はしているけど)もっと集中して取り組んでほしい‥」
と思うようになりました。
そこでちーちゃんの集中力を高めるために保育士時代の経験を思い出しながら試行錯誤した結果‥
意外にも普段の声掛けを意識するだけで子どもの集中力がぐっと変わったことを発見!
今では小3のちーちゃんはもちろん、小1のよっちゃんも平気で30分以上勉強するようになりました!
そこでこの記事では子どもの集中力を高めるための声掛けの方法を詳しく解説します!

お子さんに話しかける言葉を意識して集中力アップ!に繋げましょう!
パパ・ママの声掛けで子どもの集中力は変わる!
まさに私が実感したことです!
パパ・ママの声掛けで子どもの集中力は変わります!
なぜなら言葉は良くも悪くも相手に影響を与えますし、特に大好きなパパ・ママからの声掛けは子どもにとって大きな影響があるからです。
我が家でこんなことがありました。
家でピアノ(習い事)の練習をしていたちーちゃん。
ですがなかなか思うように弾けず、イライラし始めたちーちゃんに思わず私は

「この音はソ!」「ここはさっきも言ったド!」
などとついつい力が入った言い方になってしまい‥
結局ちーちゃんの集中力は切れてほとんど練習せずに終わってしまいました‥
私は「なんであんな言い方をしてしまったんだろう‥」と反省。
そして次の日、(練習は毎日する約束なので)仕方なく練習を始めたちーちゃんは同じく間違えイライラし始めてしまいました‥がその時!私は

おしい!そこはファじゃなくて隣のソだよ!

隣の音を弾くなんて昨日の練習を覚えていたんじゃない!すごい!
と前向きな言葉を掛けました。するとちーちゃんは

‥そうかな!
と顔が段々明るくなり、結果その日は集中して練習することができました。
(お恥ずかしい話でしたが)このようにピアノの間違えを教えるということは同じでも話す言葉や伝えるタイミングに配慮することで子どもの集中力は変わりました!
子どもにとって声掛けはやっぱり大切!ということを実感できた出来事でした。
子どもの集中力を高めるための声掛け
では子どもの集中力を高めるための声掛けとはどのようなものでしょうか‥
ここからはそんな声掛けの具体的な方法を3つご紹介します!
子どもの集中力を高めるための声掛け
- 一つのことに集中できるような声掛け
- 次にやることがわかるような声掛け
- やる気を引き出す言葉

元保育士・3児ママとしての経験を元に具体的にまとめました!
一つのことに集中できるような声掛け
子どもって目の前にたくさんのものがあるとどこに集中すればいいのかわからなくなってしまうことがあるんですよね。
例えば、幼児さんが食事中に「食べることに飽きてしまって食事が進まない‥」なんて場面はよくあると思います。
そんな時にただ

食べなさい!
と言っても子どもからすると主食・主菜・副菜など複数の食事が並ぶ中で

(いっぱいあるけど)どれを食べればいいの?
と実は混乱していたから集中できなかった‥ということがあります。
このような場合ただ「食べなさい」ではなく

(主食の)ごはんを食べよっか?
などと一つのものに限定できるような声掛けをすることで子どもは「何を食べればいいのか=何に集中すればいいのか」がわかりやすくなります。
「集中するもの」がはっきりとすれば子どもはまた一つのもの(今回はごはん)に向かって集中できるようになるでしょう。
意外と子どもの周りにはたくさんのものがあります。
そんな時は一つのもの(目の前のもの)に限定できるような声掛けをすることで子どもの集中力は変わってきます!
次にやることがわかるような声掛け
うちの子たちは集中力が切れてしまうとそれまで取り組んでいたことをすっかり忘れて違うことに夢中になってしまう‥なんてことがよくあります汗
そんな時はそれまで取り組んでいたことの「次にやることがわかるような声掛け」をするようにしています。
この声掛けで子どもはそれまで取り組んでいたことを思い出し、また続きから集中して取り組めるようになりました!
例えば、登園準備中に子どもが途中で準備をやめて遊び始めてしまったとき。
(小学生になった我が子たちは今でもすることがありますが汗)

まだお着替えしてなかったよ!

あとなんの準備が残ってる?
などとまだしていなかったこと、次にやるべきことを伝えることで子どもは登園準備に戻りやすくなります。
このように子どもが取り組んでいたことから離れてしまった時はその「次にやることがわかるような声掛け」が効果的です!
やる気を引き出す言葉
子どもの集中力を高めるためには子どものやる気を引き出す言葉を掛けることも大切です。
なぜなら子どものやる気がなければ何事も集中して取り組めないからです。
やる気をなくすNGな言葉
- 命令口調「○○しなさい」
- 焦らせるような言葉「早くして」
- 否定的な言葉「全然できてないじゃん」
やる気が出るOKな言葉
- 命令ではなく、選択肢を!「どっちにする?」
- 落ち着いて取り組める言葉「待ってるから最後までやってごらん」
- 結果ではなく課程を認める「ここまでよく頑張ったね!」
より具体的な言葉についてはこちらの記事をご覧ください!
言葉ってやっぱり大切で特に子どもにとってパパ・ママからの言葉は大きな力になります!
そして子どものやる気が上がれば集中力も高まります!
是非お子さんのやる気に繋がる言葉をたくさん掛けてあげてください!
声掛けのタイミングも重要!
子どもへの声掛けはただ言葉を掛けるのではなく、声掛けのタイミングにも注意してあげるとより効果があります!
なぜなら声掛けのタイミングを間違ってしまうだけでせっかくの集中力を途切れさせてしまう‥そんな結果になることもあるからです。
そんな子どもの集中力を高めるための声掛けのポイントは2つあります。
集中力を高めるための声掛けのポイント
- 集中力が切れかけたときに声を掛ける
- 集中しているときはそっと見守る
集中力が切れかけたとき
子どもの集中力が切れかけたときに声を掛けることで子どもはまた集中して取り組めるようになります。
先程もお伝えしたように子どもは集中力が切れるとそれまで取り組んでいたことを忘れてしまいます。
そんなときに声を掛けることで子どもは取り組んでいたことを思い出し、また集中して取り組めるようになります。

「次にやることがわかるような声掛け」でお伝えした登園準備の例はまさに「集中力が切れかけたとき」に行った声掛けです!
このように子どもの集中力が切れかけたタイミングを狙って声を掛けることで子どもはまた集中できるようになります。
そっと見守る
子どもが集中して取り組んでいるときはあえて声を掛けずにそっと見守ることでより集中できる場合もあります。
なぜなら子どもが「集中する=自分の世界に入る」そんな時に声を掛けてしまうとその声掛けがきっかけで集中力が途切れてしまうからです。
子どもが遊びに夢中になっているときは遊んでいる最中ではなく、その遊びが一段落したタイミングで

頑張ったからかっこいいものが作れたね!
などと「パパ・ママは見守っていたこと」「頑張りを認める」ような声掛けをしてあげてください!
そうすることで集中して最後まで取り組める+「パパ・ママは見ていてくれた!」という喜びや安心感に繋がります!

勉強の場面でも是非試してみてください!
さらに集中力を高めるには
「子どもの集中力を高めるための声掛けの方法」をご紹介してきましたが、私は他にも色々と取り組んできました!
「さらに子どもの集中力を高めたい!」
と思った方は是非こちらの方法も試してみてください!
3~5歳児の集中力を高める方法
小学校低学年の子の集中力を高める方法
まとめ:声掛けのポイントを踏まえて集中力を高めよう!
この記事では子どもの集中力を高めるための声掛けの重要性とそのポイントについて解説してきました!
子どもの集中力を高めるための声掛け
- 一つのことに集中できるような声掛け
- 次にやることがわかるような声掛け
- やる気を引き出す言葉
子どもの集中力を高めるための声掛けのポイント
- 集中力が切れかけたときに声を掛ける
- 集中しているときはそっと見守る
忙しいパパ・ママにとって日々の声掛け全てを意識することはなかなか大変‥
私もまだまだ実践中です!
(この記事を書きながら自分の声掛けを振り返り反省しました‥)
まずは「食事中だけ」「勉強している時だけ」など限定して行ってみると無理なくできると思います!
一緒に少しずつ声掛けを工夫してお子さんの集中力に繋げましょう!
最後までお読みいただき、ありがとうございました!


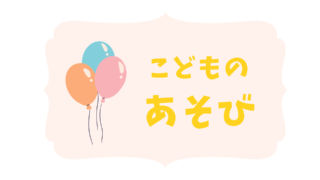

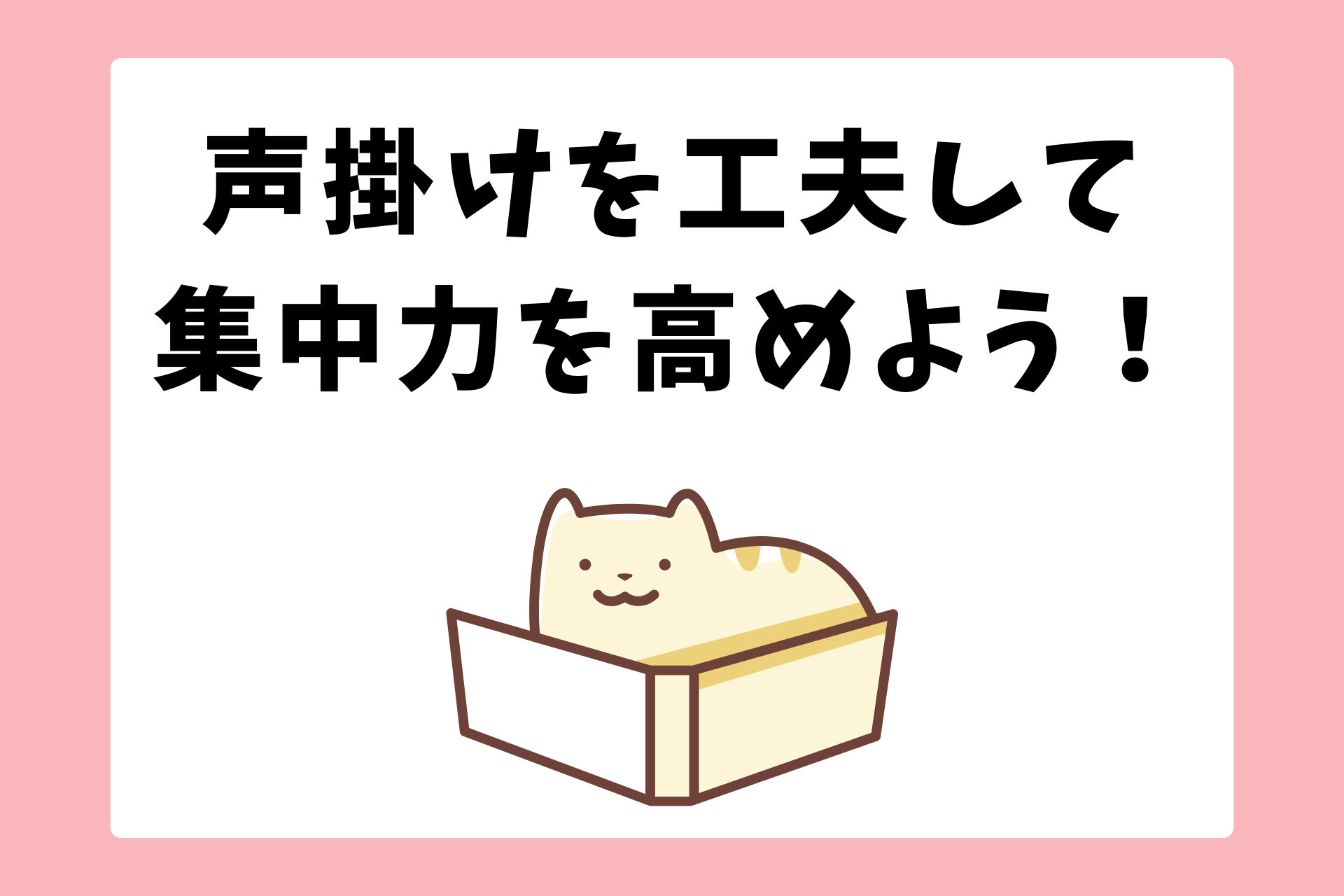

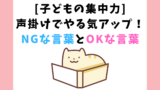
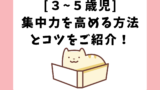
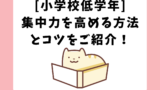

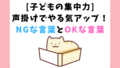
コメント