こんにちは。
元幼稚園教諭・元保育士で3児の母のちょこママと申します!
《ちーちゃん(小2)よっちゃん(年長)こーくん(1歳児)の3人の子育て真っ最中です!》
ピアノの習い事は「家での毎日の練習が必要」とよく耳にしますよね?
でも実際には
- 子どもに毎日練習させるのが大変‥
- 言われなくても自ら練習して欲しい!
こんなお悩みも持つパパ・ママもいらっしゃるのではないでしょうか?
我が家にはピアノの習い事をしている子が2人(ちーちゃん・よっちゃん)がいます。
そんな子どもたちの為に私は元幼稚園教諭・元保育士としての知識を活かし「ピアノの練習を習慣化する方法」を見つけました!
「子どものピアノの練習を習慣化する方法」の一例
- 気軽にピアノが弾けるような環境作り
- 少しでもいいから毎日ピアノに触れる!
このような方法を繰り返した結果、我が子たちは毎日自らピアノを練習するようになりました!
この記事を読むことでお子さんの「ピアノの練習を習慣化する方法」が見つかります!
そしてその方法を繰り返すことでお子さんは「毎日ピアノを練習する」ようになるでしょう!

特別難しいことはありません。是非試してみてください!
「そもそもうちの子は全く練習しない‥」とお悩みの方は下記の記事で解決策をご紹介しています。
幼児さんに向けた方法はこちらです!
小学校低学年の子に向けた方法はこちらです!
ピアノの練習は毎日必要なの?
そもそもピアノの練習は毎日必要なのでしょうか?
結論からお伝えすると私は「ピアノの練習は毎日必要!」だと思っています。
ピアノの練習を毎日した方がいい理由
- 音楽は練習を「継続」することが上達への一番の近道になるから
- 子どもは「毎日繰り返す」ことで覚えられるようになるから
例えば「毎日ごはんを食べる」ことと同じように「毎日ピアノを弾く」ことが当たり前の生活になれば子どもは自然とピアノを練習するようになるでしょう。
このように音楽面を見ても子どもの特性を見ても「ピアノの上達」には練習の「継続=習慣化」が大切になってきます。
ピアノの練習を習慣化する方法
ではどのようにすればピアノの練習の習慣が身に付くのか、その方法をお伝えします。
子どものピアノの練習を習慣化する方法
- 環境作り
- 少しでも毎日ピアノに触れる
- とにかく褒める
- ご褒美シールを上手に活用
- 練習する時間は子どもが決める
- 慣れるまではパパ・ママも練習に付き合う

我が子たちはこの方法で毎日ピアノを練習するようになりました!
「気軽にピアノが弾ける」環境作り!
私が最初に行ったことは子どもが気軽にピアノに触れられるような環境作りです。
なぜなら「子どもがすぐにピアノが弾けるような環境」があればピアノの練習がしやすくなる=練習の継続に繋がるからです。
(家のリビングはとても狭いのですが‥)我が家はリビングにピアノを置いています。
ピアノをリビングに置く理由
- 日常生活でリビングにいる時間が一番長く、気軽に弾けるから
- 常に家族の誰かがいるので安心してピアノが弾けるから
- 私が家事をしながらでもピアノを聴くことができるから
決してリビングに置くことだけが正解ではありませんが、我が家にはリビングが一番合っていました。
また環境作りの一つとして「ピアノの上や周りには物を置かない」ことも大切です。
ピアノの周りに物があるとそれらを片付けてからでなければ弾くことができません‥
またピアノの周りに物があることで集中力も欠けてしまいます‥

ピアノの周りにある物のせいで弾きにくい‥

ピアノの上になんかある!練習をやめて見てみよっと!
せっかく子どもがやる気を出しても
- 子どもにとって弾くまでの道のりが長い‥
- 遊びに繋がるようなもの(遊びの誘惑)がある
とそのやる気も失せてしまいます‥
そうならないために子どもがワンアクションでピアノが弾けるような環境作りが大切です!
少しでも毎日ピアノに触れる
練習の習慣化のためには少しでもいいから毎日ピアノに触れることが大切です。
なぜなら少しでも「毎日ピアノに触れる」ことで自然とピアノを弾くようになり、それが「ピアノの練習の習慣化」へと繋がっていくからです。
我が家も初めは一日10分程度と短い練習時間から始めました。
「練習」というよりは「課題として出された曲を一回弾いてみる」くらいからスタート。
私は一日の練習時間よりも「明日も明後日もピアノを弾く」ことを大切にしていました。
また、最初の頃は集中力が切れない(楽しんで弾いている)うちにやめるようにしていました。
子どもが「まだやりたい!」というくらいが大事!
この気持ちが「明日もピアノを弾きたい!」という気持ちに繋がり、結果我が子たちは毎日練習するようになりました!
特に練習を嫌がっているお子さんには「練習」では「ピアノで遊んでみよう」と言ってみると意外と乗ってくれることも。
「練習の習慣化」のためには最初は練習時間ではなく「毎日ピアノを弾く」ことを意識してみてください!
とにかく褒める!
「子どもを褒める!」これはピアノだけでなく、子どもとの関わりでは大切なことですよね!
なぜなら子どもはパパ・ママに褒めてもらうこと、認めてもらうことが何よりも嬉しいからです!
私は「○○ができた」という結果はもちろん、例えできなくても「その課程を頑張った」ことも認めて積極的に褒めるようにしています。
私がよく使う褒め言葉
- (たとえ数小節でも)「もうこんなに弾けるようになったの⁉」
- (楽譜を振り返り)「たくさん練習してきたね」「たくさん弾けるようになったね」
- 「こんなに弾けて天才だね!」
- 「こんな難しい曲が弾けるなんてもう○年生のお姉さんみたい!」
などともう何でも褒めます!
「大好きなパパ・ママが褒めてくれる」ことが何よりも子どものやる気に繋がります。
お子さんが喜ぶ言葉をたくさん見つけて褒め褒め名人になりましょう!

特に我が子たちは「うちに(ピアノの)天才がいる⁉」と言うとととても喜びます!
ご褒美シールを上手に活用
子どもに「継続して何かに取り組んでほしい」時にはご褒美シールやスタンプが活躍します!
なぜなら継続(毎日行う)ことは子どもはもちろん、大人でも努力がいること。
そんな自分の努力した結果がご褒美シールやスタンプを使うことで目で見て(視覚的に)わかるようになるからです。
上記で「褒めることが大切」とお伝えしましたが、「褒める」ことを視覚的に子どもに伝えるためにもご褒美シールやスタンプはおすすめです!
子どもはご褒美シールやスタンプが溜まっていくと
- 「5個もシールがたまった!」
- 「スタンプを10個もらえた!次は20個を目指すぞ!」
などと毎日頑張ってきた自分の努力を認め、「もっともらいたい!」と次への意欲に繋げることができます!
そんなご褒美シールやスタンプを効果的に活用する方法をまとめました。
ご褒美シールやスタンプを使ってみたけど「うちの子には効果がなかった‥」という方は是非参考にしてください!
ご褒美シールを効果的に活用する方法
1、より具体的な目標をもつ
ただ「毎日ピアノを弾く」という目標よりも「一日10分練習する」「課題の曲を1回ずつ弾く」などとより具体的な目標を親子で決めてください。
「どんな練習を」「どのくらいすればいいのか」と具体的にイメージすることができるようになると子どもも取り組みやすくなります!
2、練習の成果(結果)だけでなく、その努力(課程)も認める
「曲が弾けるようになったら」ではなく「今日も練習を頑張ったから」シールをあげるようにしてください。
たとえその日はまだ曲が弾けていなくても子どもは一生懸命練習しています。
いくら努力しても結果(曲が弾けるようになるなど)が出せないと褒めてもらえないとならないよう努力(課程)を認めてあげましょう!
3、たまったご褒美シールやスタンプを定期的に振り返る
シールやスタンプがたまってきたら親子でその表を見ながら練習してきた日々を振り返ってください。
「今日まで○回も練習できた!」などと自分の努力を認められれると子どもは「自信をつける→次への意欲に繋げる」ことができます!

ご褒美シールやスタンプをあげるルール(目標など)を明確にしましょう!
ご褒美シールやスタンプは使い方を工夫すれば「子どものやる気を引き出す」「やる気が継続できる」とってもいいアイテムになります!
是非使い方を工夫してお子さんの練習の習慣化へ繋げてあげましょう!
練習する時間は子どもが決める
練習の習慣化のためには子どもが練習時間を決められるようにしてあげてください。
なぜなら練習の習慣化には誰かに言われてするのではなく、子どもが自ら練習しようとする気持ちが必要だからです。
ただ、少し注意点があり、「一日の中でいつでもいいよ。」としてしまうと
- 子どもにとっては範囲が広すぎて決められない‥
- 後回しにして結局練習せずに一日が終わってしまう‥
なんてことになりかねません。
そうならないためにパパ・ママが少しだけ時間の管理を手伝う必要があります。
例えとして我が家の練習時間の決め方をご紹介します。
我が家でも練習する時間は子どもたちがそれぞれ決めていますが、一つだけお約束していることが‥それは
「ピアノの練習が終わった人からテレビ(YouTubeやゲーム)が使える」というものです。
我が家ではそもそもテレビ(YouTubeやゲーム)は夕食前までしか使えません。
そして平日は学校や幼稚園があるため、必然的に練習時間は限られてきます。
このようにすることで子どもたちは「今練習しておこう!」と自ら決められるようになりました。
子どもが練習する時間を決める方法は色々あると思います。
- 親子で話し合って練習時間を決める
- パパ・ママが一日の時間の範囲を絞ってあげる
子どもが自ら練習時間を決められるようにお子さんに合った方法でサポートしてあげましょう!
慣れるまではパパ・ママも付き合って!
子どもが毎日の練習に慣れるまでは是非パパ・ママも練習に付き合ってください!
なぜならまだ毎日の練習の習慣がない子はつい練習を忘れたり、時には練習から逃げたくなったりしてしまうからです。

でも毎日子どもの練習に付き合うなんて大変‥
と思われた方もいらっしゃると思いますが、上記でもお伝えしたように最初は10分からでいいんです!
お子さんの寝かしつけの時に毎日絵本の読み聞かせをしているパパ・ママも多いのではないでしょうか?
「子どもにピアノを教える!」ではなくそんな毎日の読み聞かせのように「子どものピアノを聴く」くらいの感覚でもいいと思います。
今は「ピアノが弾けるように!」ではなく、「毎日ピアノを弾く=練習の習慣化」ということを目標にしています。
そのためにもお子さんが慣れるまではパパ・ママも練習に付き合ってあげてください!
まとめ:継続は力なり!
お子さんが「毎日ピアノの練習をする」そんなイメージが少しでももてたでしょうか?
子どものピアノの練習を習慣化する方法
- 環境作り
- 少しでも毎日ピアノに触れる
- とにかく褒める
- ご褒美シールを上手に活用
- 練習する時間は子どもが決める
- 慣れるまではパパ・ママも練習に付き合う
効果が現れるまでは時間がかかるかもしれません。
まずはできそうなことからお子さんと一緒にチャレンジしてみてください!
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
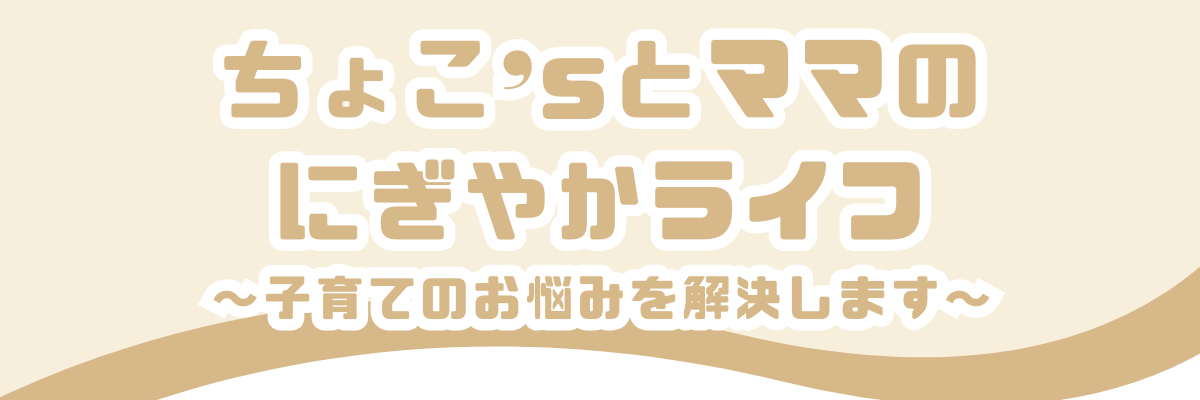



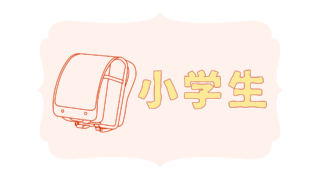
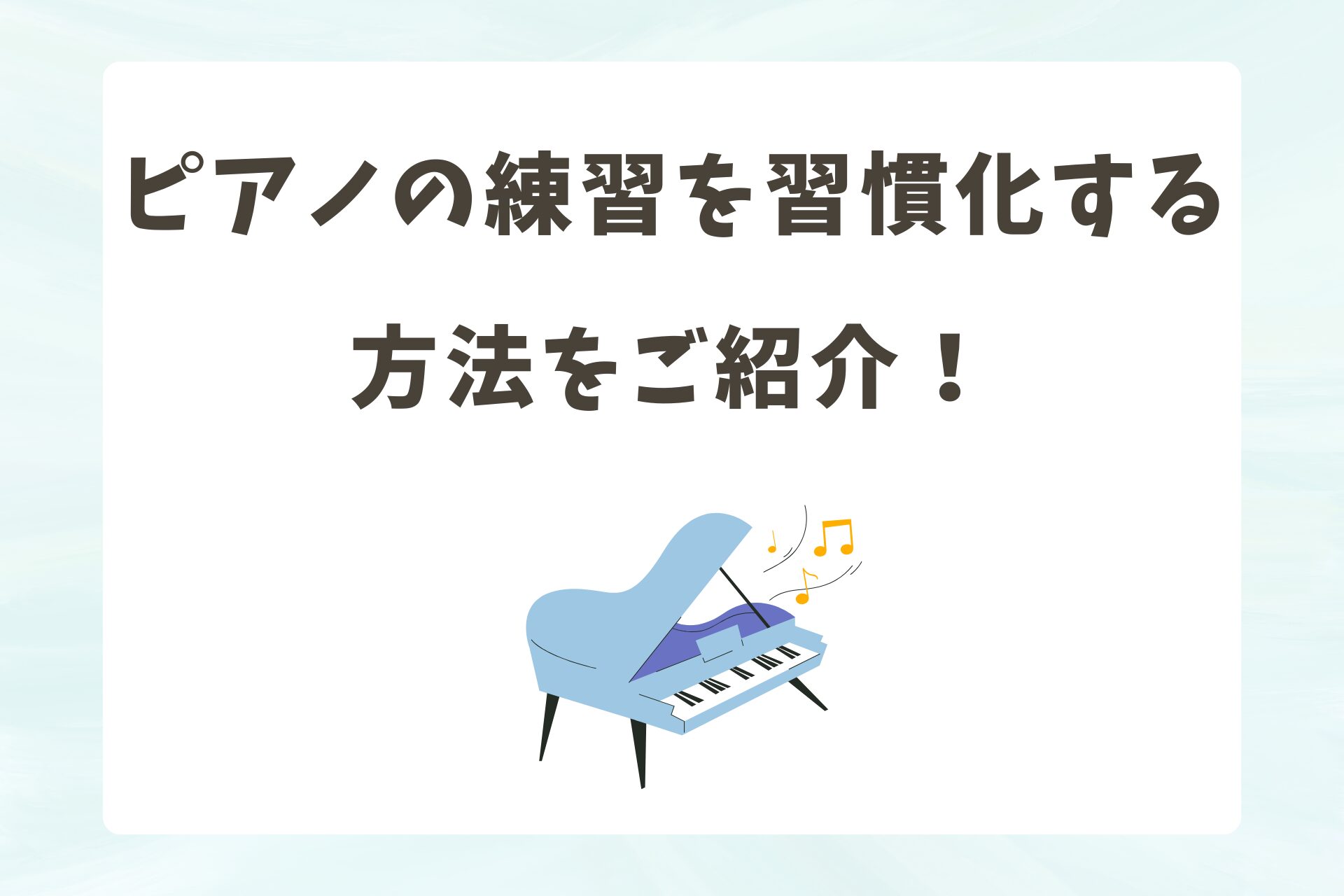
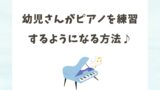


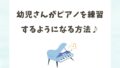
コメント